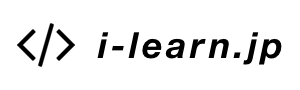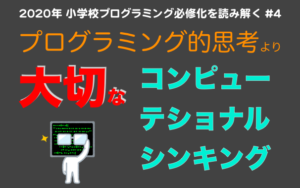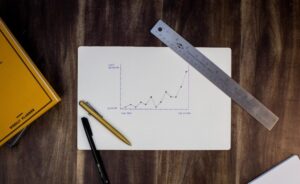こんにちは。教育ヲタ母です。
前回の顕微鏡の記事の続きです。
「ボルボックスを見つけたい」ということで、池の水を採取して顕微鏡で観察してみました。
結果はこちらです
1. 池の水を採取
池の水を旦那が採取してきました。どこの池の水かはよく分かりません。ダイソーで柄杓(ひしゃく)と米びつの容器を買ってすくってきたそうです。
なぜこんなでかい容器を買おうと思ったのか疑問です。重いしこぼれるだろうし。通常はペットボトルで十分だと思います。
2. 顕微鏡で観察!
早速、顕微鏡で観察しましょう。
スポイトで水をすくってスライドガラスの上におきます。
本来なら、カバーガラスを被せるところですが面倒なので、カバーガラスは買っていないのでナシで観察します。
観察の本では、カバーガラスを乗せるようにと書いてありますが、絶対に必要なものではありません。
カバーガラスがないことで、立体的に水滴の中を観察することができます。
カバーガラスは薄いガラスなので簡単に割れます。
幼児の場合、口に入れてしまったり、家の中に破片が散らばったり…と色々リスクが大きいと判断し、購入しませんでした。
カバーガラスを乗せないことのデメリットは、プランクトンが動き回ってしまい視界から逃げてしまうことです。カバーガラスがないということは難易度が上がります。
今回は難易度とリスクを天秤にかけて、リスクを回避することを選択しました。
で、観察です。
水の上の方①の部分をすくってみますが、プランクトンいません。
水の中②の部分ほどをすくってみますが、やはりプランクトンいません。きれいな水だから?
最後に下のゴミっぽい藻のところ③をすくってゴミと一緒にみてみると…
アオミドロと、ツボワムシっぽいプランクトンの撮影に成功しました!
3. 5歳STEM教育「顕微鏡」ー池の水の観察 まとめ
図鑑で見たプランクトンが実際に目の前にある、というのはすごい感動しますねー。顕微鏡を買ってよかったです。
水の中の藻の近くにプランクトンがいることが分かりました。もしかしたら、今年の夏は曇りが多く、日照時間が少なかったためプランクトンが全体的に少ないのかもしれません。少し陽に当てて光合成をさせてみたら増えるかもしれませんね。
また晴天が続いた後に、観察してみたいと思います。
息子はお目当のボルボックスとクンショウモが見つけられず、少しがっかりな様子でした。また別の場所の水を採取して、ボルボックス探しをしたいと思いますー。
こちらの絵本もオススメ
こういった体験を、プログラミングなどで再現するというのもすごくオススメです。再現製作は子どもの好奇心や観察力を育てます。我が家の場合は、もっぱらアイロンビーズとお絵かきです。