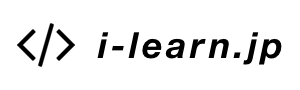こんにちは。今日もMinecraftのコンパレーターの続きです。
前回はコンパレーターの比較モードについて解説しました。今回は減算モードについての解説です。
これまでのレッドストーン回路の記事はこちらです。
▼レッドストーン回路 記事一覧
https://i-learn.jp/article/4888
1. コンパレーターの減算モード
前回の繰り返しになりますが、コンパレーターには、向きがあります。レッドストーントーチが二本の側が背面で、一本の側が正面です。
そして、正面側のレッドストーントーチが点灯している時が「減算モード」です。
減算モードは、どういうモードかというと、「背面に入力された信号の強度から、両側面に入力された信号のうち強い方の信号の強度分を減算し、正面から出力する」というモードです。
もう少しざっくりいうと
[背面の信号強度] ー [側面の信号強度] = [正面の信号強度]
です。最小値は0になります。
2. 実際に回路を作ってみよう
実際に回路を作ってみました。まずはこんな感じです。背面の回路のスイッチはオンになっています。
この回路では、コンパレーターの側面からの信号がオフになっています。なので、背面からの信号強度をそのまま正面に出力しています。また、正面から出力されてい信号の強度がわかるようにレッドストーンランプを埋め込んでいます。今、レッドストーンランプは全てついています。
レッドストーンランプが点灯する範囲=信号が届いている範囲です。
なお、水色とピンクのブロックはブロックの数がわかるようにするためのものなので、実際に回路を作る際にはなくても構いません。
では、コンパレーターの側面の回路のスイッチをオンにするとどうなるでしょうか?
正解はこちらです。
コンパレーター側面の回路をオンにすると、その分が減算された強度の信号が出力されます。その結果、レッドストーンランプが点灯する範囲が少なくなりました。
3. Minecraftでプログラミング教育したい人のためのレッドストーン回路クイズ(17)コンパレーターその2 まとめ
今回はコンパレーターの「減算モード」の仕組みについて学びました。これをどのように装置に使うのかは・・・わかりません(汗)
これから勉強して装置に組み込めるようになりたいと思います。
次回もコンパレーターのもっと便利な使い方について、解説してみたいと思いますー。